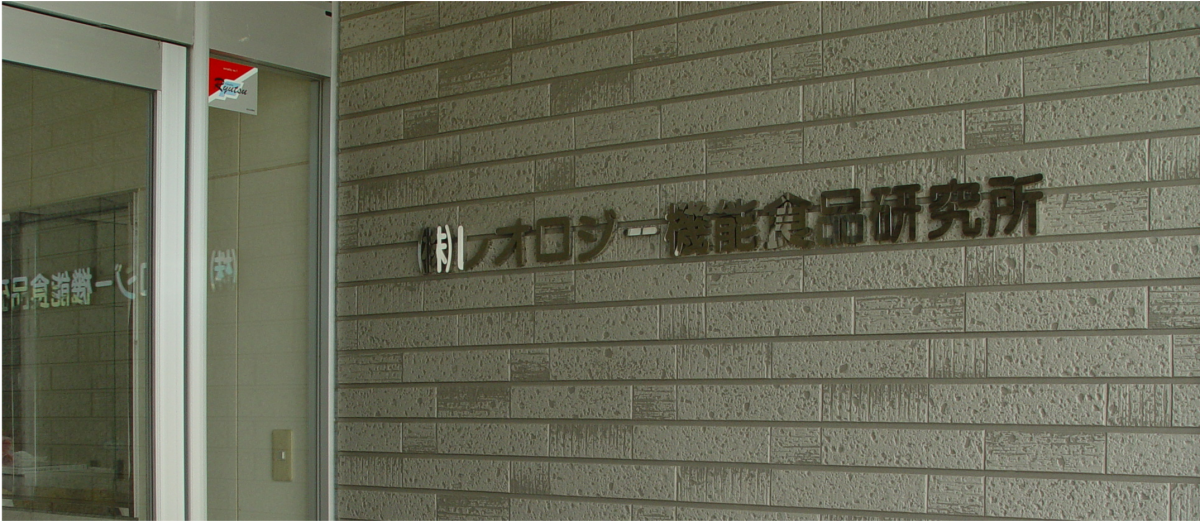BOOCSブログ
風を変えるシリーズ ~医食同源を科学する研究所のたちあげ~
2025.03.19Dr.ブログ
~医食同源を科学する研究所のたちあげ~
1990年代半ば、農林水産省は、農業や食品産業をさらに発展させるために、最新の技術を使って食べ物から役立つ成分を取り出し、それを機能性食品として活用する取り組みを進めていました。その一環として、各地に研究所を設立していました。
その頃私は、九州大学医学部第一内科と健康科学センターで、脳と心臓・血管系の関係について研究を進めていましたが、その中の研究の一つが、血液のレオロジーという分野でした。平たく言えば、血液の中の赤血球の「しなやかさ」に関する研究です。
赤血球は、酸素を体中に運ぶ大変重要な働きをしていますが、その数は血液1ミリ立方の中に500万個前後も存在します。形は円盤状で、その直径は7〜8ミクロン(1ミクロンは1ミリの1000分の1)というとても小さな細胞です。一方、動脈から静脈に移行する部位の毛細血管の直径は、さらに小さく最少直径は5ミクロンしかありません。従って、赤血球が"しなやかに"変形しなければ毛細血管が詰まってしまうことになります。もし脳で毛細血管が詰まっていけば、認知症の原因に、心臓で起これば心不全の原因になるのは明らかです。糖尿病の視力低下は、血糖値をコントロールしてもなかなか回復しませんが、その理由はこの毛細血管の詰まりを解決できていないからだと考えられます。この毛細血管は、全身の血管の90%以上を占め、その全長は地球2周半(10万km)にも及ぶと言われていますので、赤血球の"しなやかさ"がいかに重要かという事が分かります。
1995年、農林水産省はこの私の赤血球のレオロジー研究に注目し、「レオロジー機能食品研究所」を福岡県糟屋郡久山町に設立しました。この研究所は、農水省と民間企業が共同で出資した独立行政法人としてスタートしましたが、2002年には民営化され、「株式会社レオロジー機能食品研究所」となりました。このとき、九州大学を退官したこともあり私が代表に就任しました。
その後、多くの独立行政法人の研究所が閉鎖される中で、この研究所は民営化後も存続し、現在まで研究を続けています。農林水産省が掲げていた「30年先に役立つ研究」という理念は、今まさに実を結び、脳疲労と非常に深く関係している物質、プラズマローゲン研究で世界をリードする存在となっています。